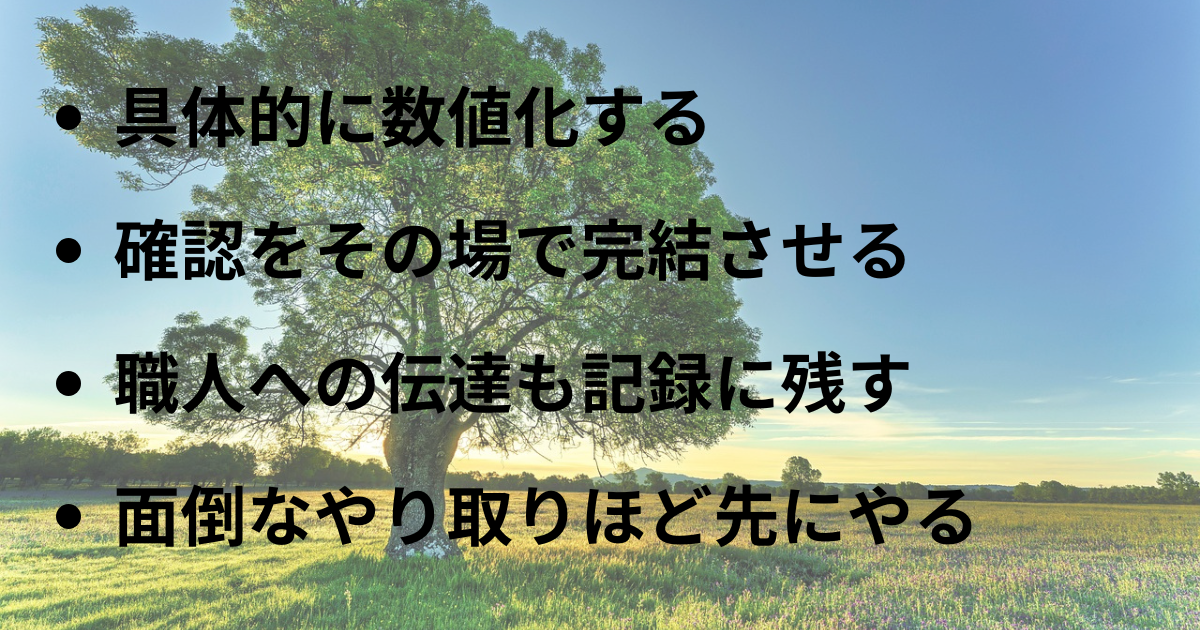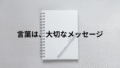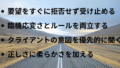お疲れ様です。
🌳電気工事、現場代理人のマサヤです🌳
ブログのテーマは「人間関係の改善」です。
現場には、個性の強い方がたくさんいらっしゃいます。
それをまとめるのは本当にたいへんですね💦
しかし、「エニアグラム」という考え方を取り入れてからは、随分楽になりました。
これをうまく使えば改善につながると思い、ブログにしています。
今回のテーマは
「タイプ9の曖昧さが招いた失敗と学び」を、現場監督を通してみていきます。
タイプ9の”魅力”
電気工事の現場で働く「佐藤さん(タイプ9)」は、穏やかで誰からも好かれる現場監督です。
彼の魅力は、チームの調和を整え、現場の平和を保ちながら物事を進めることができます。
しかし、その「平和を大切にする」ことに囚われすぎると、思わぬ失敗を引き起こしてしまいます。
■ ”曖昧な指示”が引き起こしたトラブル
ある日、クライアントから依頼がありました。
「コンセントの位置を、もう少し上げて使いやすくしてほしいんです」
佐藤さんは「分かりました、ちょっと上ですね」と笑顔で返答しました。
しかし、その場で「何センチ上げるのか」「壁面のどの範囲か」を正確に確認せず、職人に「少し上にしてください」とだけ伝えてしまったのです。
結果、取り付けられたコンセントはクライアントの希望よりも高すぎてしまい、「これじゃあ子どもが使えない」とクレームになってしまいました。
そのためやり直しが発生し、工期の遅れと費用、そして職人からの嫌味が追加されました。
■ 曖昧さの裏にある心理
タイプ9は「平和と調和」をとても大切に思います。
なので同時に「相手と波風を立てたくない」と考えてしまうクセがあります。
佐藤さんも
- 「細かく聞くとしつこいと思われるかも・・・」
- 「職人に細かいことを言うと嫌がられるかも・・・」
と考えてしまい、つい“ふんわりした伝え方”になってしまったのです。
曖昧な伝え方が大きな手戻りの原因となり、逆に人間関係の摩擦を生んでしまいました。
■ 学びと改善ポイント
この経験を通して、佐藤さんは気づきました。
「曖昧にしないことが、逆に現場を平和にする」 ということに。
次の現場からは、以下の改善を取り入れました。
- 具体的に数値化する
「少し上げる」ではなく「床から90cmの位置に」と数字を意識する - 確認をその場で完結させる
クライアントには図面や実物を示しながら「この高さでよろしいですか?」と即確認。 - 職人への伝達も記録に残す
口頭だけでなくメモや写真で残し、後から「言った・言わない」の曖昧さを防止。 - 面倒なやり取りほど先にやる
先延ばしにするとトラブルの種になるため「ちょっと聞きにくいこと」ほど早めに確認。
■ まとめ
電気工事の現場では、ほんの数センチの差が大きなトラブルにつながります。
タイプ9の「人当たりの良さ」「調和を大切にする姿勢」は素晴らしい強みですが、曖昧なまま進めてしまうと大きな損失につながります。
佐藤さんの学びは、現場監督だけでなく私たちにも大切な教訓を示しています。
「平和を守るためには、曖昧さをなくす勇気が必要」
これこそが、タイプ9が成長する大きな一歩と言えるでしょう。
あなたへの問いかけ
現場で「少し」「だいたい」「いい感じで」――そんな曖昧な表現がトラブルにつながったことはありませんか?
もし思い当たる経験があるなら、次の現場ではぜひ「数値化」「見える化」「確認の即時化」を意識してみてください。きっと仕事のスムーズさと信頼関係が変わっていきますよ。